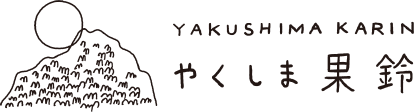屋久島の特産品 ~海の幸~

こんにちわ!ブログや広報を担当している廣瀬です。
やくしま果鈴では屋久島の特産品を使ったお土産を作ったり、売ったりしていますが、それでも店内でご紹介している特産品はほんのわずかです。
他にも美味しい物や面白い物があるのにもったいないなぁ。
そこで、島外の方にも他の屋久島の特産品を知ってもらいたいと思ったので、今回は海の幸でまとめてみました。
興味のある方は良ければご覧になって下さいね。
首折れサバとサバ節

屋久島の北部の一湊地区では、明治のころからサバ漁で盛り上がっていたんですね。もちろん水揚げされたサバは、全てサバ節として加工されていました。
でも、漁師さん達は地元のサバを生で食べる美味しさを知っていて「家族や自分用のサバの刺身」のための鮮度維持として行っていたのが、ゴマサバの首を折って、血抜きすることで鮮度を保つ「首折れ」という技法だったんです。
首折れサバにするのは、東シナ海側から日本海側で漁獲した、500g以上のゴマサバと決まっていて、ゴマサバの首折れに慣れてしまうと、マサバの方が柔らかくて少し物足りなく感じます。
今まで、屋久島ではサバと言えばサバ節の加工だけだったのが、1990年代にサバブーム(サバのブランド化)が起こり、一湊の漁師さんもこの流れに乗って「首折れサバ」が全国的に知られるようになりました。
私が初めて食べた時は、「寿司 いその香り」の握り寿司で、甘めの九州刺身醤油で頂きました。
まず、その食感に驚きます。サバって確か柔らかい刺身だったよなぁ、と思いながらコリコリする寿司を堪能しました。サバって言うより、ブリとつぶ貝の間の硬さ?もともと貝やイカのコリコリ食感が好きな私にはたまりませんでした。

また、知り合いの地元のおばちゃんがご馳走してくれた、首折れサバの刺身を食べた時は目から鱗でした。
生臭さが全然ないんです。なんでこんなに匂いがしないのかを聞くと笑いながら教えてくれました。
「さばいてから刺身に切り分けるまで、一切水を使わないんだよ。」
えっ、魚って水を使わずにさばけるの?と思いましたがキッチンペーパーをフル活用するそうです。
もともと、首折れで血抜きはされているから、出来る事だと言っていました。
今まで、何も考えずに美味しく食べていましたが、屋久島に移住してこの海の幸が近くにあることに改めて感謝しました。(おおげさ?(笑))
あら?思ったより首折れサバに熱が入っちゃいましたね。
そろそろサバ節に行きましょう!
サバ節と聞くとかつお節のサババージョンか、と思われるかもしれませんが、屋久島のサバ節はどっちかって言うとツナ缶のツナのに近いような気もします。
かつお節程硬くないので、スライスして刺身醤油で食べたり、玉ねぎスライスとマヨネーズで食べたり、そのままサラダやパスタにも使えるので、出汁として、そばやうどんに入れても美味しいです。
つまみの一つとして、上にとろけるチーズをのせて醤油と七味を一振りしてからトースターで五分。
最高です(笑)。少し熱を加える事で、サバ節の香ばしさとチーズのなんとも言えない香りが良いですね!
このサバ節は屋久島のスーパーやお土産物屋さんで販売しているので、手に入れやすいですよ。
トビウオと加工品

実は屋久島の東部、安房漁港のトビウオ漁獲量は日本一で、全国に出回っているトビウオの7割以上が屋久島産だという事はあまり知られていません。トビウオ自体は皆さんご存知なんですけど、東日本でトビウオを食べる習慣があまりない事も要因の一つなのと思います。
そして、日本の近海には30種類前後の飛び魚が回遊しているといわれ、その多くが屋久島沖を通過します。黒潮の流れに乗って季節ごとに違う種類のトビウオが捕れるので、一年を通して漁が行われています。
もともと、泳ぎの速い天敵マグロやシーラなどから逃げるために飛ぶようになったと言われるトビウオ。尾ビレで水面を叩いて飛び上がり、胸ビレを広げて数百メートル飛ぶこともあります。
そして驚く事に、トビウオには胃がなく、消化器も直線的で飛ぶために進化を遂げた、アスリートな魚です。
地元のごはん屋さんに行くと、トビウオの刺身やすり身が入ったつきあげ(練り物)、羽を広げたまま揚げた姿揚げなどがあります。刺身で食べると身は透明で筋肉質で引き締まり、酢味噌で食べるのも美味しいですよ。
お土産屋さんに行くと、魚肉を入れたおかず味噌や、燻製、みりん干し、最近ではあご出汁商品も沢山種類が出ています。
鹿児島県本土と種子島屋久島を結ぶジェットフォイル高速船の名称は、周辺地区でのトビウオの方言である「トッピー」。地域に根付いた魚であることが伺えてほんわかしますね。
トコブシと亀の手
屋久島で「磯もん」と言えば海岸周辺の岩場で捕れる貝類の事。特に「トコブシ(ナガラメ)」を指すことが多いです。「アワビの小さいの。」と言うと皆がわかるトコブシです。

地元のおじちゃん、おばちゃんはこれを狙い、独特の長さ(50cmくらい?)のある「磯ぐし」を使って取ります。岩の隙間や、穴の中にいるんですが、岩と同化しているのでプロの目じゃないと全然見つけられません。
今では数も減ってきてだんだん高くなって来ているとも聞きました。
塩ゆでしたり、醤油で煮付けたり、刺身も良いですし、炭でじっくり炙るのも美味しですよ。
そしてカメノテは、引き潮の時に干上がるような場所に群生していて、まだ採りやすい磯もんですが「見た目的に食べられない」という知人もいます。

その名の通り、亀の手に似ていることからカメノテの名付けられたそうです。
塩ゆでで食べると美味しいのにもったいないですよね。お箸を使って、チョイっと掘り出して食べるんですよ。
貝の仲間と思われがちですが、実はエビ、カニと同じ甲殻類の仲間です。
ほら、そう聞くと美味しいのかも?という気分になってくるから不思議ですよね。
みそ汁の具にしても良い出汁がでるのでお勧めです。
今回は屋久島の海の幸を簡単にご紹介してみましたがいかがでしたか?
屋久島は海が荒れたり、旬物もあるのでいつでも食べられる訳ではありませんが、旅行で屋久島に来られた際は是非食べてみて下さいね。
写真提供:川東繭右さん。島結さん。
ご協力ありがとうございました。